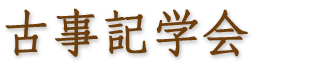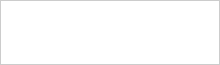令和7年度大会を開催いたします。皆様のご参加をお待ちしております。
別途、郵送される大会案内もご参照ください。
期日
令和7年6月21日(土)~23日(月)
会場
京都精華大学(〒606-8588 京都府京都市左京区岩倉木野町137)
- 叡山電鉄「京都精華大前」駅から 徒歩すぐ
- 京都市営地下鉄「国際会館」駅から スクールバスで約10分
- スクールバス乗り場:駅出口3のエスカレーターを上がって右へ約30メートル
- 日曜日は運休につき、京都バス40,50,52系統をご利用ください。
スクールバスとは乗り場が違います。
日程
6月21日(土)
理事会(11:00~12:00)黎明館(L)-103教室
講演会(13:00~17:00)黎明館(L)-101教室
開会挨拶 代表理事挨拶 神田 典城
大会校挨拶 京都精華大学学長 澤田 昌人
古事記の成立
京都大学名誉教授 木田 章義
古事記の成立を考えるためには、古事記そのものの分析が必要である。割書で示される注記は、本文制作の途中か作成後、本文に反省を加えたもので、意識的に付されたものである。「偶然」とか「書き損じて」というようなことは考えにくい。その中に特殊な注記法がある。例えば、王(女)名に対して「此(女)王以音」という注記法がある。これは六例しかないが、開化記、垂仁記に偏在している。両記の系譜では王名はさまざまな表記法で書かれており、一部の王に対してのみこの注記をとる理由がなければならない。そこで、この注記の人々の背景を探ると、丹波と関係した王ばかりであることが分かり、この注記法は、丹波関係の資料を作成した人物の手になるものらしいと分かる。おそらく古事記編纂者が丹波関係の資料の、必要な部分だけを転記したことによって、丹波資料のもとの表記が、古事記本文に紛れ込んだものと推測される。また、人名・神名の「ヒメ」は「比売」または「日女」と表記されるが、一部に「日売」表記される場合がある。「比売」は二文字とも音仮名、「日女」は訓仮名である。古事記序文に明言されているように、当時でも漢字の音と訓は明瞭に区別している。「日売」表記は音訓交用の特殊な表記法である。この「日売」表記の人々は崇神、垂仁、景行、応神、仁徳に集中する。その中で先祖を辿ることのできる七人は、尾張連の血統の人々である。これも尾張連関係の資料を、各天皇記に繰り入れるときに、もとの表記が残ったとみるしかない。
古事記では、他の文献に見られない、「以音注」という特殊な注形式が全巻に渡って使用されている。おそらく元の資料にあったものを引き継いだものが多かったと推定される。表記・注記以外にもさまざまな現象があり、それらを総合すると、古事記の本文は、古事記編纂のために集められた資料を切り継いでできあがっていることが明らかになる。
上代の動詞の活用と派生―『時代別国語大辞典上代編』の項を中心に―
大阪大学名誉教授 蜂矢 真郷
古事記の歌謡と日本書紀の歌謡とを比べるとどうなるかと、両者の最初を見ると「や くも八雲た 立ついづも出雲や へ 八重がき垣つまご 妻籠みに〈都麻碁微尒〉や へ 八重がき垣つく作るそのや へ 八重がき垣を」(記神代・一)・「や くも八雲た 立ついづも出雲や へ 八重がき垣つまご 妻籠めに〈菟磨語昧尓〉や へ 八重がき垣つく作るそのや へ 八重がき垣を」(神代紀上・一)のようで、古事記の動詞コム[籠] の連用形語尾はミ(乙類)「微」、よってそのコムは上二段活用であり、日本書紀のそれはメ(乙類)「昧」、よってそのコムは下二段活用である。
それで、まず、コム(動下二/動上二)など、上代における、終止形が同形である動詞の、活用の種類が異なる組合せは、『時代別国語大辞典上代編』に項のある動詞を全て拾ってみるとどのようであるかを、全体的に見る。そうすると、自動詞か他動詞かが重要な点と見られるので、次に、自動詞を派生するのが基本的である接尾辞ルを伴う動詞と、他動詞を派生するのが基本的である接尾辞スを伴う動詞とを全体的に見る。「一 活用の種類が異なる組合せ」「二 接尾辞ルないし接尾辞スを伴って動詞を派生するもの」「一と二とが重なるもの」の順である。
四段動詞が自動詞に、下二段動詞が他動詞になる傾向が強いが、逆に四段動詞が他動詞で下二段動詞が自動詞であるものもある程度ある。四段動詞と下二段動詞との差違は、両者が異なることを示すものであるが、明確な区別を示すように構成されたものとは言えないということと見られる。
動詞が接尾辞ルを伴った派生動詞と、動詞が接尾辞スを伴った派生動詞とは、前者は元の動詞が下二段活用のものが最も多く、後者は元の動詞が四段活用のものが最も多いことが、大きな差違として注意される。しかしながら、これは、むしろ当然であると言える。
前者に派生動詞が二音節のものはない。後者の派生動詞が二音節のものは、元の動詞が四段活用のものになく、それが下二段・上二段活用のものにある。音節数を見ると、このように気づかれることがある。
総会(16:30~17:30)
懇親会(18:30~20:30)会場 ザ・プリンス 京都宝ヶ池
- 大会会場から懇親会場行きのバスが出ます(大会会場より10分)
6月22日(日)
研究発表会(10:00~14:40)黎明館(L)-101教室
午前の部(午前10時~)
『日本霊異記』序文より編者景戒に迫る
栃木県立小山城南高等学校教諭 霧林 宏道
(司会)千葉大学教授 兼岡 理恵
『日本国現報善悪霊異記』(以下『日本霊異記』とする)の編者景戒については、『日本霊異記』下巻第三十八縁の自伝的説話に叙述があるだけで、その人物の詳細は不明である。したがって、『日本霊異記』中の説話や説話の叙述から、編者景戒に迫る方法が採られた。景戒の出自については、柳田國男氏が「物語と語り物」で景戒を小子部栖軽の末裔と指摘して以来、諸氏によって数々の氏族や紀伊国名草郡と景戒の関係が指摘されてきた。また、益田勝実氏により「私度僧の文学」という規程がなされ、景戒が私度僧であることを前提に論じられることが多くなる。その後、景戒の意識が論じられるようになる。『日本霊異記』の各巻序や説話配列から歴史意識について、下巻第三十八縁を中心に表相思想について、序並びに説話から自土意識や国家意識について、または強い政治性についての指摘があった。あるいは、上巻序の「深智の儔は内外を覯る」を踏まえ内典と外書の兼学への志向についての指摘もある。今回の発表では、『日本霊異記』の上中下巻に付された序の文体・用字・構成から、景戒の作文上の特徴をみ、景戒について考察したい。序の文体については、日本古典文学全集『日本霊異記』「解説」で「対句形式の構文」であること、寺川眞知夫氏によって四六駢儷文への志向、河野貴美子氏によって特異な字句を用いて作文する景戒の姿勢が指摘されてきた。また、平成24年には真福寺で『日本霊異記』下巻序の冒頭部分が発見され難解であった部分も訓読できるようになった。これらを踏まえつつ、『日本霊異記』の各序が、字数を整え対句を用い典故を引用する駢儷文を意識した文体であることを確認し、対句という視座から新たな訓読の可能性について提案したい。用字では、各巻序にみえる助辞「之」の用法に『日本書紀』の「之」と同様の用法がみられることを確認し、構成では上中下巻の序を網羅的にとらえてみる。加えて、奈良時代の学僧として有名な智光によって編まれた『般若心経述義』に付された序と比較しながら、『日本霊異記』編者景戒が『日本書紀』などを深く享受する環境にいたことを指摘したい。
『古事記』における「所」字の用法とその位置づけ―漢籍・仏典との比較を通じて―
厦門大学大学院博士前期課程(交換留学 筑波大学) 代 佳潤
(司会)甲南女子大学准教授 根来 麻子
『古事記』に見える「所」字の用法については、すでに先行研究において詳細な分類がなされているが、なお検討する余地が残されている。たとえば、「所」字は日本語の受身の助動詞に相当する用法を持つ(三矢重松『古事記に於ける特殊なる訓法の研究』、山口佳紀「古事記における「所」字の用法と訓読」等)と指摘されるが、そこで例示された文章を確かめると、「故、所避追而、降出雲國之肥河上」(上巻、八岐の大蛇退治)のような「所V」の構造と、「御子者、所遣之政遂應覆奏」(中巻、景行記、弟橘比売命)のような「所VN」の構造という、二つのパターンが確認される。後者の用法は「所V之N」の構造について検討されている(瀬間正之「古事記助辞用法の一端」等)が、これらの「所」字は同一の機能を担うものか、もしそうでなければ、いかなる機能を果たしているのか、さらなる検討が必要だろう。
徐江勝「論被動式中「所」字」によれば、漢文では、「為N所V」の受身文が先秦から発展したが、「所」字は単独で受身を表さないという。一方、漢訳仏典では、「所V」が頻繁に用いられ、「所」字が単独で受身を機能する例が多く見られる。こうした漢訳仏典の表現が、『古事記』の構文に影響を与えた可能性も考えられる。
本発表では、「所」字の受身用法を中心に、その句法構造に着目し、『古事記』における「所」字の用法を再考する。具体的には、漢籍や漢訳仏典における「所」字の用法や構文との比較を通じ、その用法を整理・分析する。さらに、それが日本語として独自に発展したものか、漢籍や漢訳仏典から影響を受けたものかを検討する。これにより、『古事記』における「所」字に日本語的用法が認められる一方、漢籍や漢訳仏典の語法と共通する特徴も見られ、それらの影響が反映されていることを確認する。
『古事記』垂仁天皇条ホムチワケの後日譚にみる出雲
早稲田大学教育学研究科博士課程 齊木 果穂
(司会)島根県立大学准教授 山村 桃子
『古事記』垂仁天皇条に登場するホムチワケには、出雲大神を拝し、言語を獲得した後日譚としてヒナガヒメとの婚姻譚がある。この婚姻を長野一雄氏は「不毛」と評し、西條勉氏は「この最後の『聖婚』の失敗が、皇統からの追放を意味する」と指摘するなど、ホムチワケが皇位継承をしない一因と捉える説は少なくなく、概ね首肯することができる。
本発表では、このホムチワケの皇位継承のあり方について、出雲との関係という視点を 提示したい。当該婚姻譚は、「一宿婚」という特異な場面設定のもとで、ホムチワケの「竊伺」という行為を示しながら、ヒナガヒメが「見るな」と語らず、「はぢ」を感じないなど、「見るなの禁」の定型から逸脱している。このことに関して、長野氏が「この周知の信仰習俗や表現様式を、伝承者又は『記』編者が無思慮に脱落させたとは到底考えられ」ないと指摘している通り、ここに編者の作意を認めるべきであろう。
上代における「見るなの禁」が、異界との接触、異界との隔絶といった要素を含むことを考え合わせるならば、ホムチワケの視線を受けながら、「はぢ」という感覚を覚えないヒナガヒメは、ホムチワケを自身と同一の世界に存する人物として捉えていると考えられる。一方、出雲大神をアシハラシコヲと呼称し、ヒナガヒメを「見畏」むホムチワケの行為からは、出雲に異界性を見出していると読むことができる。
このように、ホムチワケは大和王権としての視座を持ちながらも、ヒナガヒメからは出 雲に与する人物として捉えられていたのではないだろうか。そのため、『古事記』において当該婚姻譚は、大和を頂点とした王権の維持を図るためにその破綻を描き、同時に出雲から同質の存在として認められたホムチワケが皇位を継承しない理由をも示していると考える。
午後の部(午後1時10分~)
隼人曽婆訶理への「惶」~『古事記』履中天皇条における物語的意味~
愛知県立大学非常勤講師 大脇 由紀子
(司会)國學院大學教授 谷口 雅博
隼人曽婆訶理(以下、ソバカリ)は『古事記』の「歴史」叙述の中で初めて主君殺しを行う悪役として登場し、墨江中王を殺害する。彼の動機は「地位と名誉」を得るためであったが、それを依頼した水歯別命(のちの反正天皇)によって処刑される。このソバカリの殺害理由については、「義」や「信」といった儒教的概念によって論理化されていることがすでに指摘されているが、『古事記』においてこのような明確な理由説明がなされることは特異であり、その背景を『古事記』成立時の時代状況と関連づけて考えたい。
まず、履中天皇条に記される墨江中王の反逆物語において、ソバカリの登場が反正天皇の即位の正統性を補強する役割を果たしていることを確認し、特に彼が隼人である点に注目する。隼人という周縁的存在が、中央と辺境という対立構図により「異質性」を担わされ、王権の正統性を際立たせる装置となっている可能性がある。
次に、ソバカリとヤマトタケルに共通する「厠での殺害」という場面設定に注目し、「厠での殺害」が繰りかえされる意図を検討する。また、景行天皇と水歯別命の心理を表す語として用いられた「惶」の漢字表現に焦点を当て、その意味と用法を類義語「恐・畏・懼」と比較することで、その選択に筆録者独特の物語的意図が働いている可能性を指摘する。「惶」という字が景行天皇条と履中天皇条において、「王権を脅かす行為や存在を前にした心理を表す語」として選ばれている可能性を検討する。こうした字の選択には、単なる同義語の置換ではなく、筆録者独特の語彙選択の意図があると考えられ、『古事記』全体における語の配置と物語との関係性を確認する必要があると考える。履中天皇条におけるソバカリの物語は、中巻のヤマトタケルの語りを意識的に反復・変奏する構造をもち、反秩序的な存在を排除することで、王権支配の正統性を理念的に支える構想が認められる。
古事記の系譜記述の性格
東海大学教授 志水 義夫
(司会)群馬県立女子大学名誉教授 北川 和秀
記紀の基幹が、皇位継承の次第を示す「系譜」にあることは両書の構成から一目瞭然である。その記述は両書とも原則として父から子(または弟)に継承する父系系譜として表現されており、母の出自以上、子より先への系譜記述としての言及はない。しかし古事記には特殊例があり、師木津日子命の系譜(吉備津日子兄弟を経由して倭建命に至る)、日子坐王の系譜(品陀和気命の母、息長帯日売命に至る)、倭建命の系譜、忍坂日子人太子の系譜(坐崗本宮治天下之天皇に至る)などは母系を明らかにする系譜である。
この特質を『日本書紀』に照らして『古事記』の系譜的性格における特質と把握しよう。このとき『古事記』の母系系譜は『古事記』の描く天皇家系譜に〈分岐と再結合〉という閉鎖的性格を与え、それが「天皇家」を国家百姓の宗本家として定位し、所謂「八紘一宇」(『日本書紀 巻一』720)や「万世一系」(岩倉具視「王政復古議」1867→帝国憲法第一条)という世界観を描かせているということが見える。この古代から現代に至るまでの世界観は何に由来するのか。そしてなぜ『日本書紀』はそれを必要としていないのか。ここに問題の本質を置きたい。
例えば文部省『國體の本義』1937では国を家にたとえ天皇を家長とする世界観の根拠として『日本書紀』巻十四の所謂「雄略遺詔」中の文を示している(出典は『隋書』636にある)。古代中央集権国家の正史である漢文作品『日本書紀』の描く国体が学令に定める経典(『礼記』、『春秋』等)の世界観と整合性を持つであろうと見るときに、母系系譜を『古事記』の系譜記述の異質性の由来するところ――「漢意」以前の系譜的言説の必要性すなわち「天皇家」の成立条件――が浮かび上がる。
以上の図式は、相続次第を明記することで「今」を定位しようとする系譜の言説が、時系列的に『古事記』では父系と母系を必要とし、『日本書紀』では父系で充分となったことを示すであろう。そこから『古事記』の系譜記述にヤマト王権を継承する中央集権国家の長として「天皇家」であろうとする主張を読み取れよう。
閉会挨拶
皇學館大学特別教授 大島 信生
6月23日(月)
臨地研究 ※特にご案内は致しません。
宿泊案内
懇親会場のザ・プリンス京都宝ヶ池では、古事記学会会員優待で宿泊できます。
古事記学会大会 参加者専用宿泊プラン(朝食付き)